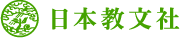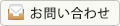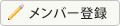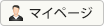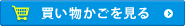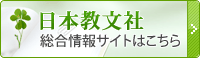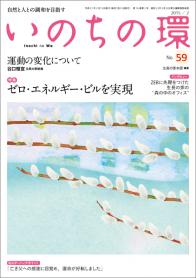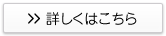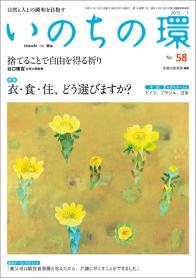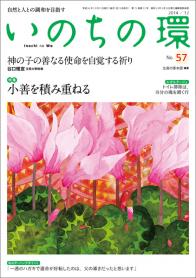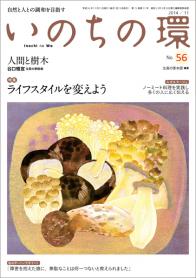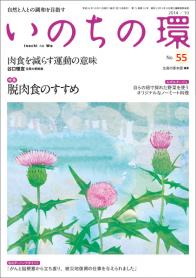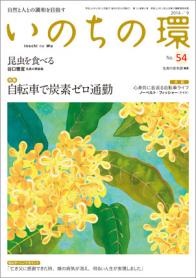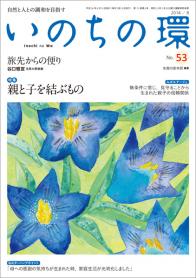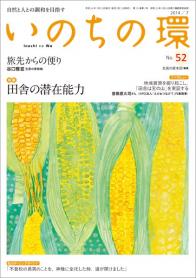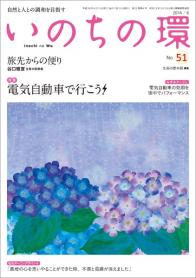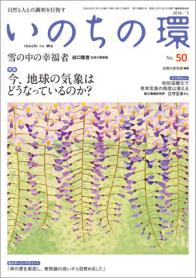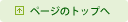定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 ゼロ・エネルギー・ビルを実現
太陽光、木質バイオマスなどの自然エネルギーや、蓄電池などを駆使した創エネ・省エネ技術により建物内の年間エネルギー使用量を実質ゼロにする日本初の「ゼロ・エネルギー・ビル」──。自然と調和したモデル社会を提示する生長の家の“森の中のオフィス”は、開所一年を経て、「ゼロ・エネルギー・ビル」を実現した。
・インタビュー1 ZEBに先鞭をつけた生長の家の“森の中のオフィス”
穴井伸二さん(清水建設(株)安全環境本部地球環境部部長)
日本初のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)を目指し、2013年に落慶した生長の家の国際本部“森の中のオフィス”は、計画通り開所一年でZEBを実現した。その建設にあたった清水建設の安全環境本部地球環境部部長である穴井伸二さんに、今回のZEB実現の意義と、ZEBに関する今後の展望などについて聞いた。
・インタビュー2 宗教的信念があってこそ達成できたZEB
渡邉重孝さん(生長の家参議・生長の家国際本部環境共生部長)
日本初のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)として建設された“森の中のオフィス”が開所後一年を経て、実際にZEBを達成した感想を聞かせてもらった。
定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 衣・食・住、どう選びますか?
何を着て、何を食べ、どんな家に住むのか。一つひとつの選択が地球や人の未来につながっています。今、私たちに求められているのは、環境に配慮した生き方です。
・手記1 「衣」──ドイツ 古い物を大切にする精神が息づく国
衣服は品質を重視して買い、何年も着ています。子供達の衣服も、姉妹で着まわしてできる限り生かすようにしている。また必要なくなった衣服は、他の人々に寄付することもある。その方法はとても簡単で、家のすぐ近くにある古着用コンテナに入れている。この古着収集システムは、ドイツのどの町にもあり、古着用コンテナに寄付された未だ十分に着られる古着が、高価な衣服を買えない人々に再利用されている。
・手記2 「食」──ブラジル 肉のない食生活で健康と生活の質が増進
まず、家庭で始めたのは、少しずつ肉の使用を減らすことだった。わが家は肉食中心だったため家族から不満も出たが、さまざまな色と味を混ぜ、見た目にも楽しい料理を作る等、工夫した。また、バルコニーに家庭菜園を作り、栽培できる範囲で野菜や穀類、ハーブなどを植えて、無農薬の作物を食べるように心がけた。
・ルポ 「住」──日本 自然との調和を意識して省エネ、エコハウスに住む
リビングに入ると、モダンなフローリングに重厚な薪ストーブが置かれている。木の階段の上にあるロフト風の2階部分も、機能性とお洒落な感覚が両立している。しかも、この家は先進的な省エネハウスなのだ。この家の構想を長年にわたって温め、実現に努力したのは、ご主人だ。若い頃からウィンドサーフィンが好きで、自然に親しんでいるうちに、自然を大切にし、環境を損なわないライフスタイルを送りたいと思うようになったという。
定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 小善を積み重ねる
トイレ掃除や、ゴミ拾いなどのボランティア活動、日々の生活のなかで、人に微笑み、優しいことばをかけること......。私たちは誰もが、人に与えるものをもっています。たとえ小さなことでも、善行を積み重ねることで、私たちの人生はより輝き、豊かなものとなるのです。
・ルポ1 トイレ掃除は、自分の魂を磨く行(ぎょう)
午前6時、分厚い雨雲に覆われ、まだ真っ暗な神社の駐車場に数台の車が到着する。車から降りてきたのは「公衆便所掃除の会」のメンバーだ。この会は、主に佐賀市の企業経営者、会社員、僧侶などさまざまな年齢、職業の有志約30人が集まり、平成22年に発足。毎週水曜日の午前6時から7時まで、佐賀市内の公園や公共施設の公衆便所の掃除を行っている。
・ルポ2 環境や人のために善いことを少しずつ
食器を洗う際は、使い古した布で油汚れを拭き取ってから、環境に負荷のかからない洗剤で洗う。花や観葉植物への水やりには、溜めた雨水を使う。生ゴミは捨てずにコンポストに入れ、肥料にするなど、環境に配慮したエコ生活を続けている。その傍ら、敬老会の手伝い、防災訓練の際の炊き出しなど婦人会の活動や、10年前に始めたクリーンウォーキングを続けるなど、地域社会にも積極的に貢献している。
定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 ライフスタイルを変えよう
環境や資源問題の観点から大量生産、大量消費型文明の転換が求められています。その転換は、毎日の小さな選択から始められます。「買い過ぎない」「持ち過ぎない」「地産地消」へ消費行動のスタイルを変えてみませんか?
・ルポ1 ノーミート料理を実践し多くの人に広く伝える
自宅から近い、高田川の堤防下にある約300坪の菜園に、仲間たち20人ほどが集まった。「普段は自分で野菜の世話をしているんですが、月に一度集まって皆で畑を耕したり、収穫したりしています。そして、自分たちで育てた無農薬野菜で、ノーミート料理を作っていただくと、それはもう格別の味わいがありますね」と、嬉しそうに語る。月3回ノーミート料理を作る勉強会を開いて、参加者とともに学びながら、その素晴らしさを伝えている。
・ルポ2 家庭菜園で野菜を育て究極の地産地消を実現
栄養士の資格を持つ専業主婦の彼女は、毎日、家族のために料理の腕を振るっている。メニューの中心は、朝、自宅庭の家庭菜園から採れた旬の野菜。採りたての野菜の美味しさは格別で、家族みんなに笑顔が広がるという。「スーパーで買ったものとは新鮮さが違うので、野菜を買うことはほとんどなくなりました。今、菜園に実っている野菜を使って、どんな料理が作れるかと考えるので、“ムダ買い”もありません」と語る。
定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 脱肉食のすすめ
牛や豚、鶏などの肉食を控えること──。いのちを大切にし、殺生をしないという宗教上の理由だけではなく、肉食が環境や飢餓問題に悪影響を及ぼしている観点から、“脱肉食”はいま、現代人に求められている生き方です。
・ルポ1 自らの畑で採れた野菜を使う、オリジナルなノーミート料理
兵庫県宝塚市の市街地から遠く離れた山林に、夫妻が、力を合わせて開墾した30坪あまりの畑がある。仕事でブータンに行ったご主人が農業に興味を持ったのがきっかけで畑作りを始めたという。採れた野菜を使ってノーミート(肉なし)料理をつくり楽しんでいる。
・ルポ2 地産地消、ノーミートの食事 穏やかで病気知らずの生活に
自然食品店に30年前から勤めている彼は、長年、肉食を控えるということだけに留まらず、玄米菜食の食生活を続けている。20歳の頃に病気で入院したことで食事の大切さを知り、マクロビオティックを学んで実践してきた。野菜を中心とした食事を心がけていると、心も穏やかになると語る。
定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 自転車で炭素ゼロ通勤
環境に負荷を与えず、しかも健康的な乗り物として、注目を集めている自転車。車や電車での通勤をやめ、自転車を使う人が増えています。風を切って走れば、見慣れた風景の中で思いがけない感動に出合えるかもしれません。
・手記 心身共に若返る自転車ライフ
古い歴史を持つドイツ、マインツの街で、妻と娘とともに暮らしている。8歳の時に親に買ってもらった自転車に乗り始めて以来、通勤も当たり前のように自転車で通い続けた。67歳になった今も、出かける際には自転車を利用し、神への感謝の言葉を唱えながらペダルを漕いでいる。
・ルポ 風を切って走る爽快感
スーツをトランクバッグに入れ、ジャージ姿にヘルメットとといういでたちで、愛用の自転車・シクロクロスバイクにまたがると、午前7時15分に自宅を出る。片道約20キロの道のりを1時間で走り、会社に到着。帰りも同じ道のりを走って家に戻るという生活を送っている。雨や雪の日は電車を利用することもあるが、この3年余り、年間を通してほぼ自転車で通勤している。どこへ行くにもできる限り自転車で出かけるという筋金入りだ。
定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 親と子を結ぶもの
人は自分の力だけで生きてきたのではなく、父親や母親とのつながりのなかで、生かされてきたのです。両親に感謝し、親と子を“結ぶもの”に思いを致すとき、新たな人生が開かれてきます。
・ルポ1 無条件に信じ、見守ることから生まれた親子の信頼関係
3世代に渡って生長の家の信仰を受け継いでいる一家がある。「父や母が、私を無条件に信じて見守ってくれているという実感があった。子供たちにも、そんな父や母の生き方を伝えられたらいいなと願っています」と話す頼もしい息子夫婦とともに、これからも一層信仰に励んでいきたいと語る。
・ルポ2 父の生き方や背中から大切なものを学んで
現在は円満そのものだが、職場で厳しい上司との軋轢に悩んだ時期があった。しかし、上司のいいところを見つけて、明るく積極的な姿勢で仕事に取り組むことで、信頼を得ることができた。教えを知らなければ心を病んでいたかもしれない、と思うと、教えを伝えてくれた両親に、改めて感謝の思いが湧いた。
定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 田舎の潜在能力
手入れされていない森林や耕作放棄地などが目立つ田舎……。しかし、発想を変え、そうした自然資源を活用するとき、田舎は“宝の山”に変わります。無限の潜在力を秘めているのが日本の田舎なのです。
・インタビュー 地域資源を掘り起こし、「田舎は宝の山」を実証する
曽根原久司さん(NPO法人「えがおつなげて」代表理事)
過疎化、高齢化、離農、耕作放棄地や荒れた森林の増加……。こうした田舎の現状を逆手に取り、地域資源の掘り起こしを行って成果を挙げているのが、NPO法人「えがおつなげて」代表理事の曽根原久司さん。「日本の田舎は宝の山。農村の資源を活用すれば、10兆円の産業と100万人の雇用創出が可能」と語る曽根原さんに、田舎の持つ潜在能力について聞いた。
・ルポ 耕作放棄地を復活させ、個性的な米作りを進める
親から田んぼを受け継いで米作りをしながら、5年前までは県庁職員として農業基盤整備事業の一環である土地改良の仕事をしてきた。その中で、今、増えつつある耕作放棄地を何とか復活できないかと考えるようになり、定年退職後、中山間地域にある谷筋の耕作放棄地を購入して、自然と調和した農業に取り組むようになった。
定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 電気自動車で行こう!
地球温暖化の原因となるCO2、大気汚染をもたらすNO x(窒素酸化物)、PM(粒子状物質)を出さない電気自動車は、地球や人に負荷を与えないエコカーです。脱石油社会、低炭素社会の実現に向け、あなたも電気自動車で走ってみませんか。
・ルポ1 電気自動車の効用を街中でパフォーマンス
オフィス前の駐車場には、ちょっと変わった車が停めてある。トヨタ自動車が超小型EVとして展開している一人乗りの電気自動車「コムス」だ。
コムスは、可愛らしい外観で、実にコンパクト。普通の自動車の半分ほどのスペースで駐車できる。コンビニエンスストアの宅配サービスに導入され始めているので、街角で見かけることも多くなったが、県内では彼が導入第一号である。
・ルポ2 地球を汚さないEVで走ると気分爽快に
三菱の電気自動車(=EV)「i─MiEV(アイミーブ)」に乗って3年になる。「乗り始めたらいいことばかり」と言う彼女に、EVの魅力を聞いてみた。
定価:352円(税・送料込)
環境・資源・平和の問題を解決し、芸術表現の喜びを広げる生長の家の総合誌!
特集 今、地球の気象はどうなっているのか?
酷暑、ゲリラ豪雨、大寒波など、自然災害が多発し、異変が起きている地球。今、地球の気象はどうなっているのか。IPCC第5次評価報告書の主執筆者である気鋭の気象専門家に、現状を聞いた。
・インタビュー 地球温暖化で異常気象の頻度は増える
国立環境研究所 ・地球環境研究センター気候変動リスク評価研究室長
江守正多さんに聞く
巨大台風、竜巻、記録的な猛暑、豪雨、大雪、大干ばつ……。これまでに経験したことがない“異常気象”に見舞われている地球の気象は、今、どうなっているのか。その大きな要因と言われる温暖化の現状はどうなのか──。国立環境研究所の江守正多・地球環境研究センター気候変動リスク評価研究室長に聞いた。